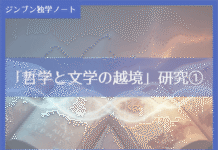ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十回となる今回のインタビューでは、失われた技術を求め、自らの手で古代の窯を復元しながら謎多き渥美古窯の探究を続ける陶芸家、稲吉オサムさんにお話を伺います。
探究心の原点と独自の哲学の形成
——本日はよろしくお願いします。稲吉さんのInstagramやホームページなどを拝見しましたが、謎に満ちた渥美古窯(あつみこよう)を探求されている、という印象です。
迫っているのか、迫られているのか分かりませんが、そんな毎日です。
——まさに歴史のミステリーに挑んでいらっしゃる。今日はその原点から、稲吉さんご自身の物語に迫っていきたいと思います。まずは読者のために、渥美古窯との出会いから教えていただけますか。
これだ、という劇的な出会いがあったわけではないんです。24歳くらいの時に瀬戸の学校で焼き物を学び始めて、25、6歳で弟子入りをして。その後、地元である豊橋の隣町、田原市博物館で【渥美古窯】の壺を見た時に、衝撃を受けたのが始まりですね。もう20年くらい前のことです。
——もともと焼き物の道に?
全く焼き物作家とかになるつもりもなく、専門学校の先生にお前は先生の所に弟子入りして修業してこいと何も考えずに連れていかれました。弟子入りといっても、やっていたのはほとんど掃除と運転ばかりでした。いわゆる丁稚奉公ですね。自分の考えは一切捨てて、「はい」しか言わない。他の言葉を忘れてしまうくらいでした。
——職人の世界の厳しさが伝わってきます。幼い頃から、ものづくりがお好きだったのでしょうか。プロフィールを拝見すると、野山を駆け巡り、模型作りに熱中する少年だったとか。
オタクまっしぐら、という感じでしたね。一人で遊ぶのが好きで、セミを捕りに行ったり、川で魚を釣ったり。プラモデル作りも、今思えば今の仕事に繋がっているのかもしれません。
——インドアとアウトドアのバランスが絶妙ですね。
当時は理由なんてなく、ただ好きで、性に合っていただけだと思います。
——稲吉さんのこれまでの歩みは、いわゆる「順当に敷かれたレールの上」とは少し違う印象を受けました。
高校中退なので、そもそもレールというものを知らないのかもしれません(笑)。
——そのあたりを、ぜひ深掘りさせてください。一般的なルートから外れることに、不安はありませんでしたか。
不安しかないです。ですが、やりたいことが次から次へと出てくるので、一人でいることが気にならないのかもしれません。
——学校生活はいかがでしたか。得意な科目、苦手な科目はありましたか。
得意だったのは、やはり図工でしょうか。逆に算数は今でも本当に苦手で。国語も全然ダメでした。とにかく勉強が嫌で、今でも嫌いです(笑)。
——かなり尖っていらっしゃいますね(笑)。
自分ではそんなことないと思っています(笑)。ただ自分で経験して、体を通してでないと、なかなか理解も納得もできないんです。そうすることで初めて、次に進める。例えばどこか現場へ行くにしても、まず自分で調べて、自分の足でその場所へ行くことで、距離感や空気感が分かる。そういう準備、段取りを考えるのが好きなのかもしれません。
——旅行の計画を立てるのが好きなタイプですね。
どっちもやりますが、正直なところ、どっちもストレスです。誰かやってくれよ、と(笑)。でも、どうせやるなら、嫌なことも全部楽しむ方向に考えを切り替えるようになりました。いつの間にか、そういう思考になっていましたね。
次回は渥美古窯との出会いについて伺います。