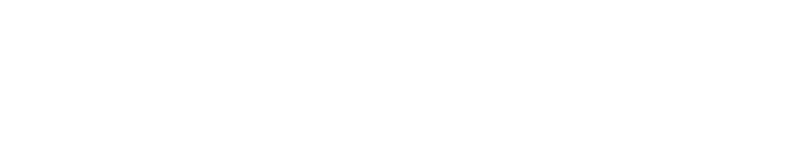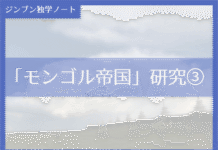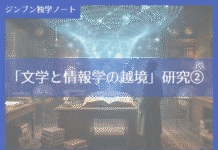ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十七回となる今回のインタビューでは、古典文学と視覚文化の交差領域を探究し、絵巻物から現代のポップカルチャーまで幅広い視点で「受容」の歴史を読み解く、永井久美子先生にお話を伺います。
古典と現代を繋ぐ「受容」の視点と問い続ける力
——それでも研究を「続けたい」と思われた原動力は、どこにあったのでしょうか。先生の中には、何か尽きることのない渇望のようなものがあるのでしょうか。
卒論も修士論文も、書き上げてから「まだ物足りない」「自分はまだまだだな」という気持ちがあって。学会発表でも、終えてから「これで終わると中途半端だ」「ここで終えたくないな」という気持ちがわいてくる。その連続なんです。
別に完璧主義者のつもりもないし、特段、負けず嫌いなわけでもないと思うのですが、ここで終わるの悔しいな、とか。分かりたいな、まだ分かってないな、というのがずっとあります。
——いやいや、負けず嫌いと言っていいと思います。粘り強さがありますね。
納豆の国(茨城県)の出身なのは影響があるのか分からないんですけれども(笑)。
粘り強いというよりかは、単に「終わりたくないな」というのがずっとある。それは今もそうです。まだまだ世界は分からないことがあるし、なんなら自分のことだって分かりきったわけではない。
専門にしよう、仕事どうしよう、となった時に、結局考えるのは、「自分は何ができるのか」「自分は何者か」「自分は今の社会で何ができるのか」「この社会はどういうものか」という、自分自身と、自分を取り巻く世界についての考察や分析なのかなと思います。まだ自分の知らない世界があるなら、私は知りたいですし。よく、好奇心が強いとか、意外と行動力あるよね、とは言われます。
——研究テーマについてもうかがいます。先生のご研究は、絵巻物から世界三大美人言説、作家の肖像イメージ、そして最近ではゴジラまで、一見すると大きくジャンプしているように見えます。ご自身の中では、これらを貫く一貫した関心というものはあるのでしょうか?
絵巻研究の人が急にゴジラ、ってどれだけ飛ぶのか、と思いますよね。とはいえ、特に庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』は比較的分かりやすく、日本の神話や古典をふまえています。例えば、映画の終盤に出てくる、ゴジラを倒すための「ヤシオリ作戦」には、ヤマタノオロチ退治の物語が重ねられています。「大蛇に酒を飲ませる」という日本神話の物語を、現代の映画の中で受容・表象した、面白い事例だと思います。そういう、長く読み継がれ、語り伝えられてきた物語が、近現代にどう蘇るのか、ということに関心があるんです。
——古典に何が書かれているか以上に、近現代にどう「受容」「表象」されるか、という点ですね。
そうです。「世界三大美人」の言説研究も、似たような流れですね。私は、顔が「平安風だ」と言われることが昔からあり、個人的な体験からではありますが、現代と平安とでは「美人観」は異なるのか、という疑問がわきました。自分は何者かと考えた時に、素朴な疑問の一つとして、「平安時代と現代はどう繋がっているんだろうか」と言うのが出てくる。
——なるほど。「古典」と「現代」を、「ビジュアル」や「イメージ」を切り口に接続していく、というのが先生のスタイルなのですね。平安時代の絵巻物を研究することが、なぜ「人間とは何か」「自分とは何か」という問いに繋がるのか、読者は疑問に思うかもしれません。その接続点に、まさに「現代」という視点がある。
私は時代を超えた「接続」が気になり続けているタイプです。一方で、「古文を勉強すること自体は楽しいけれども、現代社会とどういうつながりを持つことができるのか、具体的なイメージが持ちにくいかもしれない」という、高校生の頃に抱いた不安も、正直まだ残っています。古典文学と現代と断絶がまったくないとはいえない。でも、古典を学ぶことに意義を見出せない人も少なくないそんな社会のあり方への疑問も、同時にもっているんです。
中学時代に「平安風の顔だ」と言われて、古臭いのかな、と落ち込んだ自分を救いたい、みたいな思いもある気はしますね。これまでに複数の高校生から、「美人観の歴史」を探究学習で扱っています、と何度か質問ももらってきました。こと「容姿」については、いろんな方に響くテーマなのかな、とは思っています。
——まさに「自分ごと」として捉えられるテーマですね。
やはり自分は何者か、世界とどう接続できるのかを知るための方法として、人文学はあると思っています。
最近、ビジネスパーソンのための哲学や美術の入門書も多いですよね。それはやはり、生きる意味とは、と考える時に、ギリシャ哲学などの先達を通じて、自分を知り、世界の見方を知りたいということなんでしょうね。
——お話をうかがっていると、先生は日常の「当たり前」とされていることにも、常に問いを立てていらっしゃるように感じます。
そうですね。「世界三美人言説」が一例ですが、「子供の頃に聞いた気がするけど、誰が言い出したのか」と調べてみたら、よく分からないことが分かりました、と。
誰も調べてないから自分で調べます、みたいなのは好きだと思います。素朴な疑問を、どう学術的な「問い」にできるのかが、研究においては大切になってきますね。「問い」の立て方については、『問うとはどういうことか』(梶谷真司・著)という本は、大変参考になると思います。
研究者にならなくても、「問う」ことや「書く」ことって、自己表現であり、コミュニケーションだと思うんです。自分は何者かを伝え、それによって社会と結びつきを持つという点で。私の場合はそれが、平安時代やそれ以前のイメージが近現代にどう継承されているのか、特にどうビジュアル化されているのか、という枠組みでした。
人それぞれ、同じ場所にいても、見ているものが違ったりするのは、面白いことですよね。自分の中から出てくる疑問、自分が特に強く抱く興味関心を、見落とさず、大切にしていくのが良いと思います。
——本日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。