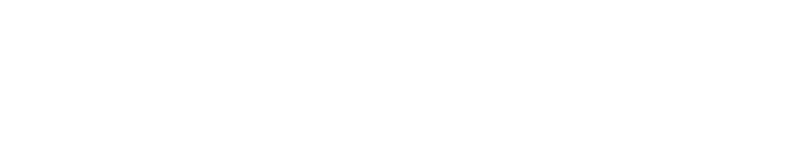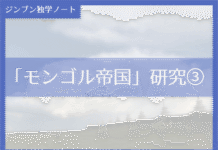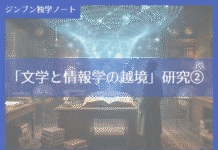ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十七回となる今回のインタビューでは、古典文学と視覚文化の交差領域を探究し、絵巻物から現代のポップカルチャーまで幅広い視点で「受容」の歴史を読み解く、永井久美子先生にお話を伺います。
「文学と美術」の狭間での葛藤と学際的アプローチの選択
——「人間について知りたい」という探究心を持って、学部はどのように選ばれたのですか?
それもギリギリまで迷いがちで。いま私は、東京大学の進学情報センターというところで学生さんの進路相談の仕事もしているんですが、学生から、就職や「実学」を意識した相談をよく受けます。
卒業後の未来を気にする気持ちは、すごくよく分かります。私も、公務員になった方がいいのかなとか、法学部や経済学部の方がいいのかなとか、社会科学系も嫌いではなかったので、多くの候補があり迷いました。
文学部にも、すごく惹かれるものがありました。ただ、次の話はあくまでも当時に自分にとっては、ですが、独立した各学科の専門性が高いことから、文学、もしくは美術のいずれかに分野を絞った場合、自分の興味の一面は深められるけれども、切り捨てるものが多すぎはしないかと迷ってしまい、一つを選ぶということがずっとできずにいて、そんな時に教養学部のガイダンスに出て相談をしてみたら、「文学と美術、絞れない? 絞る必要ないですよ、両方やればいいんです」と言われて。
——「両方やればいいんです」、ずいぶん明快な答えですね。
「ここにはジャンル間交渉の研究をしてきた先達がいる」と聞いて、そんな世界があるのか、と驚きました。選ばない道がある、全部取っていい世界がある、と目から鱗が落ちる思いでしたね。
それで結局、教養学部の比較日本文化論というコースに進学しました。現在は、学科は再編成されています。学際性が強いコースで、いろんな専門の同級生や先輩、後輩がいました。さまざまな授業が取れる面白さがあり、ジャンルとか別に決めなくてよかったんだ、というのはすごく楽しかったですね。
——そもそも東京大学を選ばれたのも、入学後の進学選択で進路を選ぶ時間がある、という側面が大きかったのでしょうか。
まあ、それはなくはないですね。考える時間が持てる、というのは。早く決断して専門性を身につけた方がいい、という考え方も大切ですが、私にとっては入学してからも色々学べるのは惹かれたところかもしれません。また、率直に言えば、興味のあった分野ではあるけれども、人文学は、学んでどういう職業に就けるのか具体的なビジョンがなかなか持てず、選ぶ勇気を持てるまでの時間がほしかった、というのもあるかもしれません。
——確かに、今の学生さんにとっても切実な悩みですね。
今、学生さんの相談を受けていても、当時の自分と重なるところがあります。
もし、悩んでいらっしゃる読者の方がいたら、早い遅い自体を問題にして自分を責めない方がいいですよ、と伝えたいです。考える時間が必要なタイプなのかもしれませんからね。
そのうえで、「よく分からないけど、なんかやっぱりモヤモヤして、分かりたいから飛び込んでみようかな」というのも、ありだと思いますよ。
——中高生の頃から「文学とビジュアル」というご関心が一貫しているように感じますが、大学に入ってからも、その軸はぶれませんでしたか?
そうですね。ただ、文学にもビジュアルにも、それぞれの専門家がいる世界で、自分に何かできるのか、ということには悩み続けました。たとえば、作品の背景となる歴史について学ぼうと、日本史学専修課程の研究室に行ってみたりする。するとそこには、高校生の頃から古文書を勉強しています、みたいな学生がいたりして。各分野に、上には上がいるだろう、と実感するわけです。やはり、専門性の高い分野には、本当にその分野が好きで得意な人がそれぞれいる。そうなると、自分にできることって何だろう、と考えますよね。
一方で、自分のできることでやっていく道を選んだら、今度は「器用貧乏にならないだろうか」と心配になる。とあるグルメな先生が、「『創作日本料理』と言うけれど、それは一度名店などで日本料理を徹底的に修行した人が新たな境地を切り拓くならいいが、できることだけでやっているのは本格的ではない」という旨をおっしゃっていて。それはすごく心に残っています。
——うーん、厳しいお言葉ですね。
できないから逃げる、というのも違うなと。それで、文学部の授業にも出席して文学や美術、歴史、それぞれの深い世界を垣間見たりもしました。各分野の専門性は、とてもリスペクトしています。
ただ、やはり明治期に大学が創設された頃の学問分野の分類に沿って、文学は文学、美術は美術、とそれぞれ専門性を高めていこうとなった時に、こぼれ落ちてしまうものがある。例えば挿絵が入った一つの作品としてまとまっているものを、それぞれ「文章」と「挿絵」に分割して研究する、ということでよいのかという疑問です。もちろん、それによって深まるものもあるとはいえ、この作品を研究したい、という時の喪失感をどうしたらいいんだろう、と。
補足しておくと、文学部においても、学際的な研究は、今日、可能ではあると思います。ただ、学生の頃の自分は、迷ってしまった。教養学部は居心地が良かったけれど、文学部などのプロフェッショナルな人たちに敵わないから「学際的」という言葉に逃げてるだけなのではないか、とか。正直、すごく色々考えました。
——専門性に対する葛藤があったのですね。「学際性」は、研究者としてのキャリアを考えた時、不安にはなりませんでしたか?
なりました。博士課程に進学して、初めて学会で発表した時のことを今でも思い出します。
学会では、絵巻物をどう研究できるのか、文学と絵画の分析をうまく交渉させて両方から考察していきたい、といった内容の発表をしました。そうしたら、とある先生が「果たしてそれは何学なのか、就職する時に困らないかな、大丈夫かな」と心配してくださって。ああ、学生の時の選択だけじゃなくて、今度は仕事として「何の分野の教員になれるのか」問題が起きるんだな、と。発表を終えた途端にまた別の不安が、というのはありましたね。
——学会デビューで、いきなりアイデンティティを問われるような。
言ってみれば学会デビューって、例えば「〇〇研究の分野で今、こういう若手がいます」という、いわば社交界デビューみたいな意味があると思うんですが、私は果たしてデビューできたんだろうか、と。海の物とも山の物ともつかないけど、とりあえず頑張ったね、みたいな感じだったんじゃないか、と思いましたね。
最後は具体的な研究テーマについて伺います。