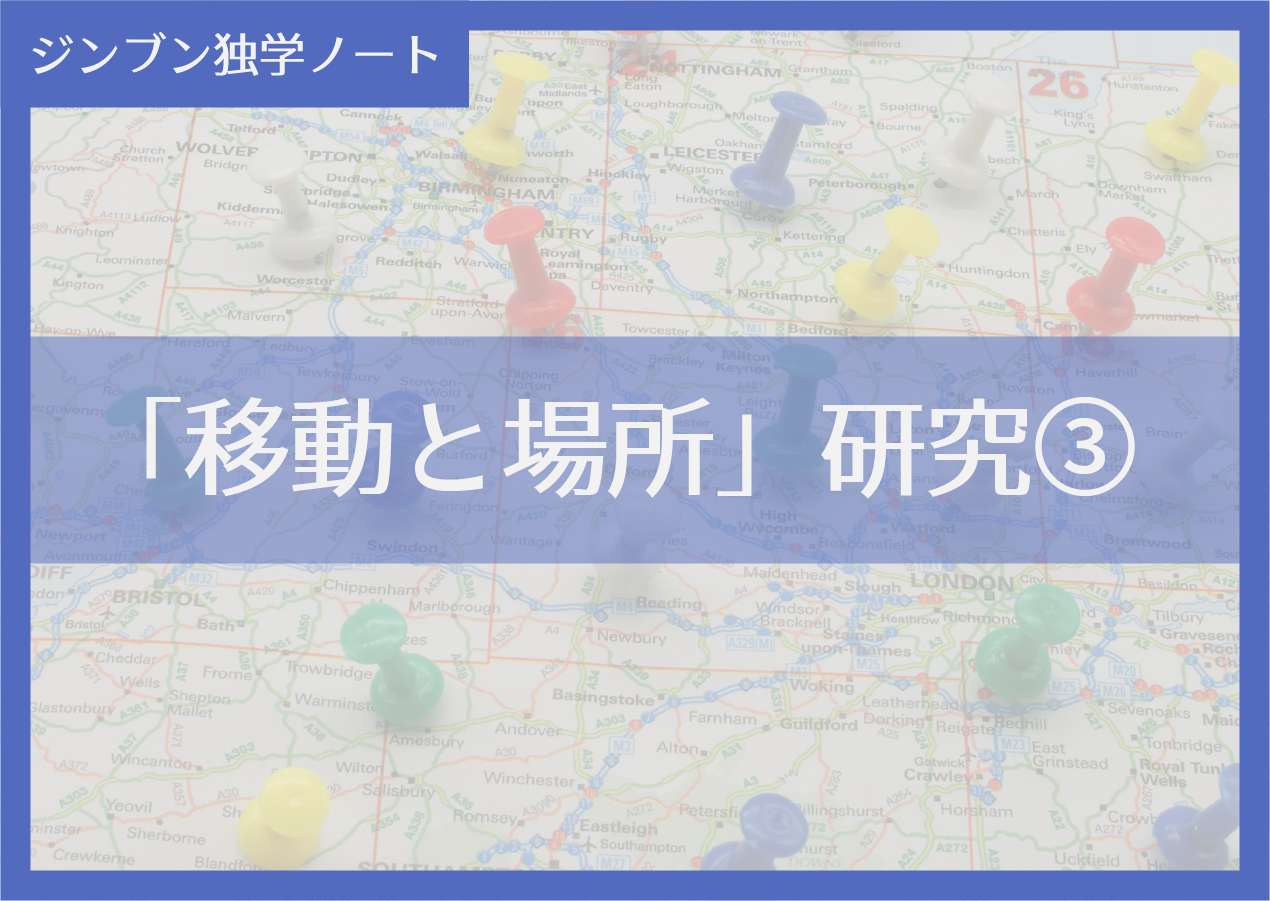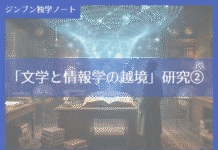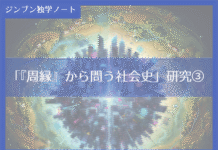ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十七回となる今回のインタビューでは、現代人の「移動」と「場所」との関わりをテーマに研究を進める、東京大学の住吉康大さんにお話を伺います。人文地理学の視点から、フィールドワークや「日記調査」といったユニークな手法で人々の生の声に耳を傾け、固定観念としての「場所」を捉え直す、その独自の研究アプローチに迫ります。
伝えること、問い続けること――探究の旅は続く
——現在は助教として、ご自身の探求で得た気づきを、今度は学生たちに伝える立場だそうですが、担当してみていかがですか。
今年から大学で、1年生向けの初年次ゼミを担当しています。高校までの「正解を探す学び」から、「自分で問いを立てる学び」へと転換する最初のステップなので、伝え方の難しさを痛感していますね。
例えば、先行研究の文献を読む時。大学院レベルになると、その研究の論理的な弱点を指摘したり、残された課題を見つけ出したりする、いわゆる「批判的な読み方」が求められます。でも1年生の多くは、まず書かれている内容に対して「なるほど、そうなのか」と感想を抱いてしまう。その違いを伝えるのが、まず難しい。あるいは、レポートのテーマが「環境問題をなくすには」といった、人生をかけても厳しいような壮大なものになってしまったり。問いを立て、扱えるサイズに分解していくことにも、知識と技術がいるのだと改めて感じます。
思えば、私自身がそういう「やり方」を明確に教わった記憶はありません。どちらかというと「背中で見て学べ」という環境で、先生は多くを教えず、学生が自力でたどり着くのを待つ、というスタイルでした。それも一つの教育ですが、自分が教える立場になったからには、そのプロセスを少しでも言語化し、再現性のある形で伝えていけないかと模索しているところです。
——研究者として、また教育者として、ご自身の関心は今後どのように広がっていきそうでしょうか。
場所と、そこに関わる人の感情や記憶、経験といった繋がりへの関心は、これからも持ち続けると思います。ただ、それが「移動している人」に限定されるかは分かりません。
一方で、自分の研究が、いわゆる「キラキラした移動」のようなポジティブな側面ばかりを見ているのではないか、という葛藤もあります。世の中には、難民や、映画『ノマドランド』[1] … Continue readingで描かれたような人々、あるいは派遣労働者のように、望まない形で移動を強いられている人々も大勢います。そうした現実を前に、自分の研究がどうあるべきか。両方を扱うべきなのか、それとも…。まだ答えは出ていませんが、目を背けてはいけないテーマだと感じています。
——現代の日本でも、望まない移動の代表例として「全国転勤」がありますね。
そうなんです。地理学の分野にいると、どこへ行くことにも面白さを見出す人々の集まりなので、「転勤が嫌だ」という感覚が、正直なところ最初はよく分かりませんでした。でも、世の中の多くの人はそうではない。そうした感覚とのズレや、自分の共感力の限界も感じています。すべてを自分で研究できるわけではありませんが、そうした「ポジティブではない移動」とどう向き合っていくかは、今後の大きな課題です。
——最後に、住吉さんにとって、10年以上過ごされてきた駒場キャンパスはどのような場所ですか。
いろんな意味で、すごく「奇妙な空間」だと思います。渋谷から2駅という都心にありながら、どこか隔絶されている。大学の敷地は贅沢に使われていますが、周りにはいわゆる学生街がなく、学生が気軽に住める家賃相場でもない。
そして、そこにいる人々が非常に均質的で、しかも短いサイクルで入れ替わっていく。井の頭線に乗っていても、10年も経つと「あ、この人は駒場で降りるな」というのが大体分かるようになります(笑)。でも、その学生たちは2年でごっそりと本郷キャンパスへ移ってしまう。そのせいか、サークルの伝統が途絶えやすかったり、立て看板に描かれるテーマが短いスパンで移り変わったり。長くいると、自分だけが取り残されていくような、時が進んでいくような感覚を覚えることもあります。
一方で、近隣の住民の方々が普通に通り道として使っている。そんな光景もまた、この場所の特殊さを物語っています。個人的には、ずっと同じ建物にいて、自分で掃除をしたり手を入れたりもしているので、居心地はいいですし、愛着もありますが、やはり不思議な場所ですね。
——場所の体験が、時間の流れやそこでの振る舞いによって変化していくというのが、本日のお話全体を貫くテーマのようにも感じました。ご自身の研究や経験から紡がれる、生々しく新鮮な「場所」のお話、これからも楽しみにしています。本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
References
| ↑1 | 2021年の映画。リーマンショックで仕事と家を失った女性が、現代のノマドとして車上生活を送る姿を描く。2017年の米国のノンフィクション『ノマド: 漂流する高齢労働者たち』に基づいている。 |
|---|