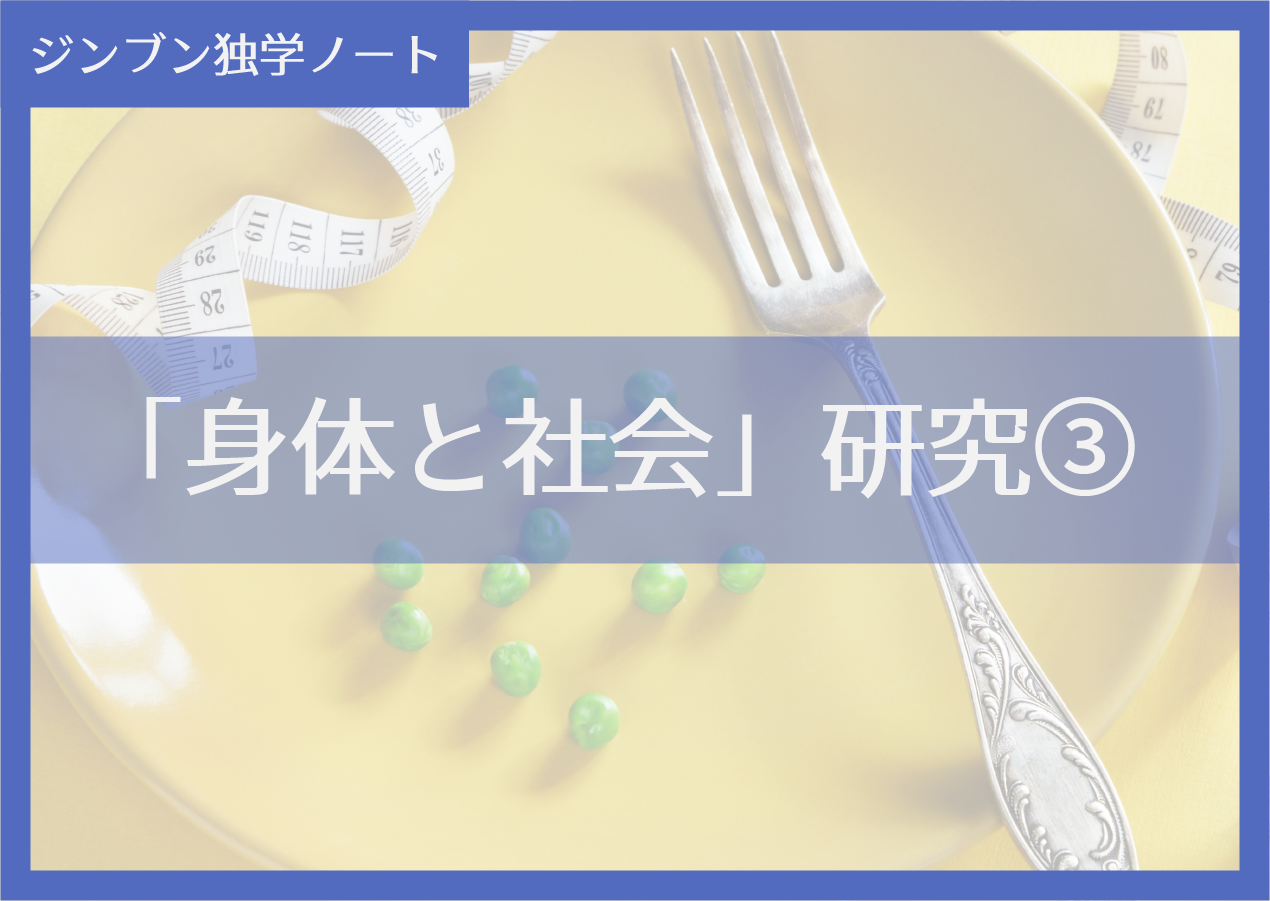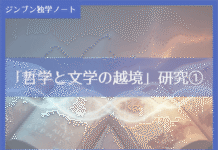ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十三回となる今回のインタビューでは、山田理絵先生にお話をうかがいます。山田先生は東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生哲学講座の特任助教として、摂食障害やタトゥーの研究を行う傍ら、シンポジウムやワークショップの企画を行っていらっしゃいます。
研究テーマとの出会い
——国際関係学と、社会学。二つの領域を横断し始めたというこということですね。最終的には、どちらをメインで取り組むことになるんでしょう?
大学時代は社会学の授業は受けていたものの、専門としては国際関係学の勉強をしていましたので、メインはずっと国際関係学です。
二年生の時に国際法のゼミに入れていただき、国際法に関する卒業論文をまとめました。卒業論文は、「クローン技術規制の国際的同行と慣習法形成要件に関する考察」というタイトルで、クローン技術の利用とその国際的規制の動向について議論しました。
——ご自身では、卒業論文の手ごたえはどうでしたか?
当時はとにかく精一杯書き上げるという感じでしたね。国際法および国際関係学については本当に初歩中の初歩の勉強だったと思いますし、私自身も関心が色々な方向に拡散していたので、あまりできもよくなかったとは思います…。ただ、この領域に関する資料や論文の探し方や調べ方を学び、国際的なルールの運用やそれを下支えする思想を学べたことは、とてもよい経験となりました。お世話になった先生方にも大変感謝しております。
—— 調べる技術は基礎体力みたいなものですものね。あ、そういえば、在学中に留学はされたんでしたっけ?
結局、留学はしませんでした。
その代わり、筑波大学の学類の一部で採用されている「早期卒業制度」を利用しました。一定の基準を満たせば、大学を3年で卒業できる制度です。入学後に制度のことを知り、先生方に相談しながら単位取得やゼミの参加を少しずつ前倒しにしていきました。大学には2009年4月に入学して、2012年3月に3年生で卒業することができました。
卒業後の進路を決める段階で、また色々と迷走する時期もあるのですが、最終的にやはりもっと社会学の専門的な議論を学んでみたいと思い、同じく筑波大学の人文社会系研究科の社会学専攻に進学しました。
—— では、いよいよ大学院に進学して、本格的に社会学に取り組んでいくことになります。引き続き、「病と社会」が中心テーマになっていくのでしょうか。
はい。修士課程から取り組み始めた研究テーマが「摂食障害」についてでした。
摂食障害は、アメリカやヨーロッパなどの国々で戦後増加した精神疾患で、特に女性が患うことが多いとされてきました。「西洋の病気」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、日本でも似たような状況で、戦後に精神医学的な研究の論文の数が少しずつ増加しました。また、70年代、80年代、90年代と、どんどんと患者が可視化されていきました。
社会学の摂食障害へのアプローチは色々とあります。例えば、「摂食障害になる個人の心理・生物学的な問題」よりも、「人々を摂食障害に誘い込むような社会的な背景」に焦点を探求したり、医療や心理的アプローチの枠組みの外にある、回復のあり方を探求します。また、特定の食行動がいかにして歴史的に治療や研究の対象になってきたかといったことを検討するアプローチもあります。
私が研究をスタートした頃、社会学領域における日本の摂食障害の研究として、浅野(澤田)千恵先生の『女はなぜ痩せようとするのか——摂食障害とジェンダー』(勁草書房、1996年)、加藤まどか先生の『拒食と過食の社会学——交差する現代社会の規範』(岩波書店、2004年)、過食症に焦点を当てた、『ソシオロジ』掲載論文である團田浩二先生の「『吐く』という社会的行為」(2000年)などを読みました。また、摂食障害からの回復過程に焦点を当てた、中村英代先生の『摂食障害の語り——〈回復〉の臨床社会学』(新曜社、2011年)が当時出版されたばかりでした。当事者の方へのインタビューを中心とした重厚な先行研究に感銘を受け、いつか私もこのような研究がしたいと思いました。
—— では、ここからどんなふうに研究を進めていくんでしょうか。
修士課程に入る時に研究計画を提出しますので、入学前までに、研究するテーマ、具体的な問いや仮説についてはある程度整理されていなくてはなりません。
ただ、修士課程に進学して以降も、引き続き、先行研究や方法論の勉強を重ねていきますので、そこで研究計画を修正しつつ、資料やデータの収集を進めていくのが一般的かと思います。
私の場合は、医療社会学のほか、文化社会学、歴史社会学、逸脱行動論、ジェンダー論や家族社会学などに関連するものを勉強しました。また、社会学に限らず、精神医学、心理学はもちろん、医療やメンタルヘルスのことを扱う人類学や歴史研究も参照しました。
——ちなみに、修士論文では、具体的にどんなテーマに取り組んだのですか?
2014年に提出した修士課程では「摂食障害はどのように語られてきたのか—新聞を中心とした通時的語りの考察—」というタイトルで論文をまとめました。1876 年から2013 年までの『朝日新聞』 、『読売新聞』 、『毎日新聞』と、補足的に1970 年以降の『日本経済新聞』を分析対象として、<摂食障害という現象のどのような側面が社会問題として語られてきたか>ということと、<特に近年のマス・メディアにおける摂食障害の語りの特徴とは何か>ということを検討しました。
—— 新聞! 意外なメディアが登場しました。
新聞を対象とした社会学の研究は色々とありますが、私が修士論文の中で直接参照させていただいたのは、歴史社会学の研究者である佐藤雅浩先生が2013年に刊行された『精神疾患言説の歴史社会学:「心の病」はなぜ流行するのか』(新曜社、2013年)というご著書です。
様々な精神疾患が大衆言説の中で隆盛したり衰退したりするメカニズムについて、百年分以上の新聞を対象として分析された、重厚な研究です。
出版されたばかりの同書を読んで、感銘を受けました。そして、摂食障害の研究にも応用できないかと考えて、似たような視点、方法論での研究を行ってみました。
最終回は現在の取組について伺います。